もはや会話の枕詞となっている“コロナ”。
降ってわいたこの災いから一番打撃を受けているのは、やっぱり外食業界ではないか。これ以前にも、若者の外食離れ、 会社の飲食経費の削減、 中食・家食への流れ・・・・とボディーブローを受け続けてきた外食シーンは、消費税増税によるジャブからの、新型コロナというフィニッシュブローを食らうことになってしまった。
すでに知り合いの飲食店さんからも「店をたたむことにした」というノックアウト宣言がチラホラと聞こえてくる。
今後も廃業する店舗が増えることは間違いないだろうけど、この世の中に飲食店が必要なのは間違いないと確信している。
普段味わえない料理が食べられる場所であるはもちろん・・・
普段話せない事も思い切って話せる場所。
見知らぬ人同士が気軽に会話を交わせる場所。
男女問わず新たな出会いがある場所。
交わされる会話に新たな発見がある場所。
自分だけのネットワークを構築できる場所。
プライベートにおける自らの居場所 。
そんな場所は、やっぱり飲食店しかないでしょ、と思う。
私自身も、過去飲食店で得たネットワークは様々な場面で助けとなってくれた。
ということで、
コロナという災禍をものともせず、今後の関西外食シーンを盛り上げようとしているキーパーソンに会い、彼らがどんな未来を描いているのかを探ってきた。
KGB編集長 宮本昭仁
「株式会社 鯖や 」右田兄弟とは

「株式会社 鯖や」として、サバの加工食品の製造販売を行い、株式会社SABARとして「とろさば料理専門店SABAR(サバー)」を国内20店舗・海外2店舗を展開。
サバを地域産品とした地域活性プロジェクトをいくつも成功させてきたのが、会社の代表で一般社団法人日本さば文化協会代表理事、そして “サバ博士”である右田孝宣(みぎたたかのぶ・以下右田兄)氏、そして副社長の右田孝哲(みぎたたかのり・以下右田弟)氏の兄弟だ。

――まずは「株式会社 鯖や」「株式会社SABAR」の現状を教えてください。
「株式会社 鯖や」は、サバの総合商社です。商品開発から製造、卸、販売まで行っています。そして2015年にクラウドファウンディングでサバの専門店『 SABAR 』を開業しました。
――現在は何店舗まで展開されているのですか?
右田兄「国内が20店舗、シンガポールに2店舗あります」
地域ならではの新たな養殖サバを次々ブランディング
――右田さんのお名前は、この飲食店の創業者としてはもちろん、自治体や大手企業との連携によるさまざまな地域活性プロジェクトで聞くことが多くなりましたね。
右田兄「2015年にJR西日本様が鳥取県と共同開発 で『 お嬢サバ 』を開発したのが最初ですね。陸上養殖で寄生虫が付きにくいことから、このネーミングにしました(笑)。JR西日本がサバの養殖事業に取り組んだことで話題となりましたね」

――それが食べられる店もオープンされましたね。
右田兄
「そうです。 カウンター前に巨大な水槽が設置されていて、泳ぎ回るサバを楽しめる“ サバの水族館 ”というコンセプトの店を南森町に作りました。 いくらサバをブランディングして有名にしたところで、それが食べられる実店舗がなければ意味がありませんから」
「モノを作ったからといって売れる時代ではありません。その魅力を消費者の方々にどう伝えていくかが重要。そしてモノを作って消費者の方々にお届けするまでの流れを作る必要があると考えています」

福井県の小浜では「よっぱらいサバ」
――2018年には、福井県・小浜市で「よっぱらいサバ」というブランドを展開されましたよね。
右田兄
「もともと小浜は 若狭湾の海産物、特にサバを京都に運んだ通称“ 鯖街道 ”起点でした。昭和49年には3500トンぐらいの漁獲量があり、浜焼きサバ、へしこ、なれずしなどサバを使った郷土料理も全国的に知られていました。しかし乱獲などの影響で2015年にはサバの漁獲量が1トンにも満たない状態になってしまって。もやはサバ市場の90%はノルウェー産という事態になってしまっています」
――そこで 小浜市が2016年「鯖、復活」プロジェクトをスタートさせたんですよね。かつて大漁で賑わった小浜のサバ漁を、養殖によって復活させようという試み。
右田兄
「はい。それで僕のところに協力の要請があったんです。この養殖サバを立派なブランドサバに育てて欲しいと」
――それが「よっぱらいサバ」ということですね。
右田兄
「そうです。 鯖街道の入り口は小浜ですが、出口は京都の出町柳。その出町柳に340年の歴史を持つ『 松井酒造 』という酒蔵があり、そこの力を貸していただきました。そして…」
①鯖街道入口の小浜で作られた酒米を、出口の出町柳で日本酒にする
②その製造工程で出た酒粕を、今度は小浜に持って行ってサバの餌に加える
③酒粕の入った餌で育ったので「酔っぱらいサバ」と命名
④クラウドファウンディングで3800万ぐらいを集めて、このサバが食べられる店として「とろさば料理専門店 SABAR」の小浜の田烏店、そして阪急三番街店、京都烏丸店、東京銀座店の計4店舗を作る。
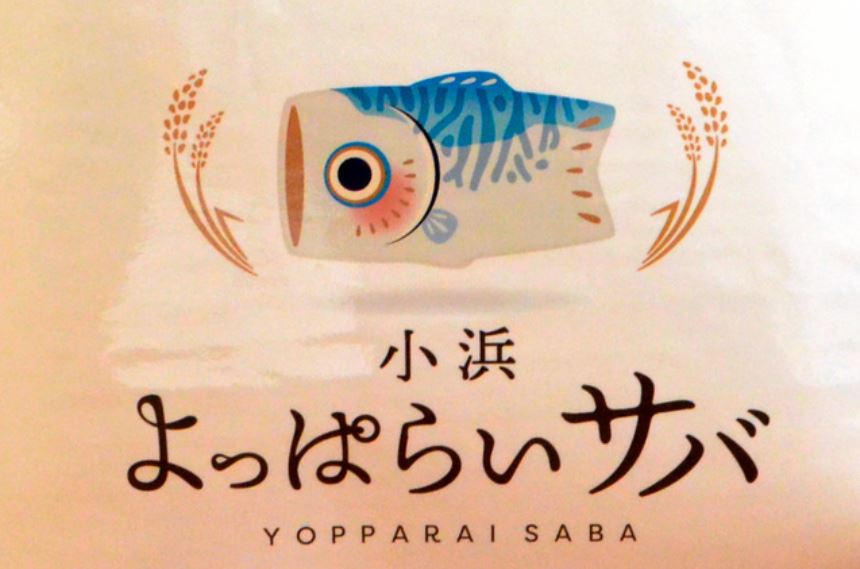
右田兄
「…というストーリーで展開しました。京都の烏丸店では、小浜にある『 御食国若狭おばま食文化館 』から歴史の展示物を借りてきてそれを展示するスペースを作ったり、店内に『 さば神社 』も作っておみくじが引けるようにしたり・・・お客さんが楽しみつつ、かつて鯖街道の起点として栄えた小浜の現状を知ってもらえるような店作りにしたのです」

右田兄
「このように、サバを地域産品としてブランディングしてお客さんに届くまでの道筋を作り、結果として地域への理解を広めることで、地域振興に役立てる試みをしています」
鯖の製造卸や、飲食店経営の枠から外れまくって進んでいく右田さん。料理と酒を出す場所としての飲食店に生産者や地域と消費者を結ぶ接点としての役割が付与されている。そしてその集大成としてオープンしたのが、和歌山にある“ SABARビレッジ ”だ。後編では、その“SABARビレッジ ”について語ってもらう。








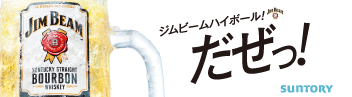
![プライバシーマーク[2002397]](/wp-content/uploads/2019/03/20002397_200_JP.png)